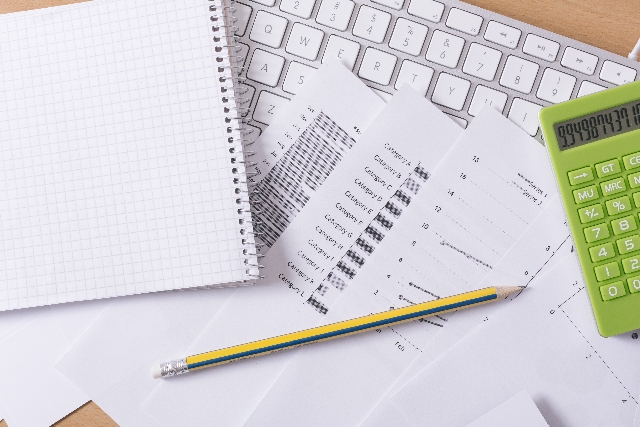(5)敷金
アパートやマンションの敷金を差し入れている場合は、その差し入れている敷金の金額を記載します。
これは、敷金はアパートやマンションの退去時には返還されるお金ですので、「資産」としての価値があるためです。
もっとも、敷金があるからといってすべて裁判所に「資産」として取り上げられるわけではなく、居住用のアパートやマンションの敷金については、敷金を家主に請求してしまうと住む場所を追い出されてしまうので、通常は居住用の住居にかかる敷金については「資産」と判断されて回収されることはありません(※居住用ではないマンションやアパートなどの敷金については資産と判断されますので、通常は賃貸借契約を解除されて敷金を回収し、債権者に分配されることになります)。
なお、契約書に敷引き条項などがあって、退去時に返還される可能性の無い敷金であっても記載する必要があります。
この場合は、「回収不能の理由」の欄に「敷引き条項があるため」などと記載しておけばOKです。
関西の方では、敷金ではなく「保証金」と呼ばれている場合もありますが、その「保証金」が「敷金」と同様に退去の際に返還されるべきお金として差し入れられている場合は、資産として記載する必要があります。
≪東京地裁の場合≫
東京地裁の場合には、敷金や過払い金などについては別途設けられている「その他、破産管財人の調査によって回収が可能となる財産」に記載することになっているようです。
敷金や過払い金などは各裁判所によって記載する欄が若干異なっていますので注意してください。
(6)過払い金
借金の利息を払い過ぎた場合などに発生する「過払い金」があれば、その金額も記載する必要があります。
過払い金は、自己破産の申し立てをする段階で回収途中であったり、回収前であったりする場合が多いと思いますが、過払い金が発生している場合には、回収の有無にかかわらず、その金額を全て記載しなければなりません。
≪東京地裁の場合≫
東京地裁の場合には、敷金や過払い金などについては別途設けられている「その他、破産管財人の調査によって回収が可能となる財産」に記載することになっているようです。
敷金や過払い金などは各裁判所によって記載する欄が若干異なっていますので注意してください。
(7)未払いになっている給料(賃金)
勤務している会社が給料の未払い状態になっている場合には、その未払い分の給料については会社に対して請求することができることから「請求権」となり、未払いになっている給料の総額をこの欄に記載する必要があります。
給料については資産説明書の「収入」の欄に記載することが必要ですが、「未払い給料」がある場合にはその「収入」の欄とは別にこの「請求権」の欄にも記載する必要がありますので注意してください。
(8)その他
上記の他にも、たとえば「誰かに殴られた」というような場合は治療費や慰謝料請求権などが発生していますので、その金額を記載します。
また、「振り込め詐欺にあった」というような場合は、そのだまし取られたお金を記載しなければなりません。
とにかく、誰かに「お金を返せ」とか「お金を支払え」という権利がある場合は、その相手方・金額・回収見込みの有無・回収見込みがない場合はその理由を記載しなければなりません。
「回収見込」の意味
「回収見込」の項目には、その請求権の回収が出来そうか、出来なさそうかをおおよその予測で記載しておけばよいでしょう。
例えば、街でナンパされた男に10万円をだまし取られたが、その男の住所や名前が分かっておらず、警察に被害届を出してもいっこうに逮捕される見込みがないなどという場合は、おそらくだまし取られた10万円を取り戻す見込みはないと思われますから「回収見込」の欄には「☑無」にチェックを入れておけばよいでしょう。
どちらか分からない場合は「☑無」にチェックしておこう
回収する見込みが有るか無いかその予測がつかない場合や、回収する見込みが五分五分の場合は、「☑無」にチェックを入れておく方がいいと思います。
なぜなら、回収見込を「☑有」にチェックを入れてしまうと、裁判所が「お金を回収できそうだな、じゃあ管財人を選任して管財人に回収してもらおう」と判断して破産管財人が選任される「管財事件」として処理されてしまう可能性があります。
裁判所は回収できるお金は回収して債権者に分配する使命を持っていますから、回収見込みがありそうな財産を見つけたら、破産管財人を選任する「管財事件」で処理します。
管財事件では破産管財人が選任され、その管財人の報酬(最低20万円程度)は自己破産の申し立てをする人の負担となりますから、自己破産を申し立てる側としては、できるだけ破産管財人が選任され無い方が安く自己破産できます。
≫同時廃止と破産管財事件 – 破産管財人が選任される場合とは?
そのため、回収する見込みとしてはっきり「有」と言えないような場合は、「☑無」にチェックを入れておく方がいいでしょう。
※但し、回収する見込みが有るのにウソをついて「☑無」とチェックを入れるのは、説明義務違反として刑事罰の対象となります(犯罪となる)ので注意が必要です。
時効にかかる場合であっても記載する
一般的な債権の時効は10年となっていますが、時効期間が経過して請求できないような場合であっても資産として記載しなければなりません。
これは、時効で消滅するような請求権(債権)であっても、時効期間が経過すれば当然に自動的に消滅するものではなく、相手方が「それは時効にかかっているから返さない」と返答した場合(これを時効の援用といいます)に初めてその債権が時効によって消滅することになるからです。
時効にかかる請求権(債権)であっても、相手方が時効の援用をするまでは債権としての資産価値がありますので、自己破産の申立書に「資産」としてあげないといけません。
もっとも、このような場合は「回収不能」といえますので、「回収不能の理由」の欄に、「〇年の消滅時効にかかるため」などと記載しておきましょう。
資産説明書の「貸金・求償金など」の欄の具体的な記載例
例えば、平成27年3月1日に自己破産の申し立てをする場合において、友人の同級生太郎が自分の名前を勝手に使って消費者金融のX社から20万円借りておきながら失踪したため、同級生太郎に代わって平成26年12月1日に利息も含め21万円を返済した場合の記載例は次のようになります。
相手方 金額 発生時期 回収見込 回収不能の理由 同級生太郎 21万円 H26/12/1 □有 ☑無 行方不明のため ~